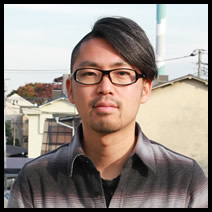フォトグラファー大橋 仁
1972年生まれ、神奈川県出身。92年「写真新世紀」で優秀賞を受賞しデビュー。99年に写真集『目のまえのつづき』、05年に『いま』(共に青幻社)を発表。Mr.ChildrenやビョークなどのアーティストのCDジャケットを撮影し、雑誌、CDジャケットや広告写真、CMやPVの動画の撮影も手がける。
- 使用タブレット
- Intuos4
- 使用歴
- 知人に勧められたため
- きっかけ
家族、血、出産、娼婦、別れた彼女。力強いフレーミングと生々しい描写でそれらを捉え、鮮烈な写真を多数発表してきたフォトグラファー、大橋仁さん。どの作品も感情の躍動が表出した、些細な(時に重大な)一瞬が濃縮されています。そんな大橋さんはアシンメトリーな髪型がトレードマーク。「完全に飽きるまでこの髪型でいきます」と笑う大橋さんですが、制作の原点や魅力的な作品を生み出す秘訣はどこにあるのでしょう? このたび、9年前から住んでいるという自宅兼事務所にお邪魔し、そのヒミツに迫りました。
テキスト・田島太陽
撮影:CINRA編集部
強烈な処女写真集とアラーキー

自殺をはかって倒れている継父を発見し、まず救急車を呼ぶ。そして次に搬送される継父や血まみれのベッドにカメラを向け、シャッターを切る。99年に発表した初の写真集『目のまえのつづき』に収録されているのは、そんな衝撃的な写真群です。
「現場で他にすることがなかったんです。母はパニック状態だったし、継父はもう気絶していて。その時、この光景は撮るしかない、撮らないといけないと思いました」
強烈な印象を残すカットをまじえながら、家族の日常を中心として構成された『目のまえのつづき』は各所で話題を呼び、大橋さんのキャリアを語るうえで欠かせないものとなりました。ただ、継父の写真を収録するのは、かなり葛藤があったそう。
「読者からの反発もあるだろうとは思っていたし、かなり悩みました。でも、自分で納得できるものにしないと意味がないかなって、ある日吹っ切れたんです。ただ、もし継父があのまま死んでいたら外していたとは思います。幸運にも立ち直ってくれて、今も元気で生きてくれているから、これは出してもいいんだなと思って決断しました」
大橋さんが写真を始めたのは19歳。当時は特にやりたいことも定まらず、「就職率がいい」と知人に聞いた専門学校に入りグラフィックデザインを学んでいました。しかしデザインにはあまり興味を抱くことはなく、「何かを創る仕事がしたい」という漠然とした考えから絵を公募展に送ったり、華道を習ったりしていた時期も。父親のカメラで撮った写真を賞に応募したのも、そんな腕試しのひとつでした。兄が買っていた雑誌『写真時代』に掲載されている荒木経惟さんの写真を少年時代から読み耽っていた大橋さんにとって、写真はごく日常的なものであり、「写真新世紀」に応募したのも敬愛する荒木さんが審査員を務めていたからでした。
その荒木さんが、大橋さんの写真を佳作に選んだことで、本格的に写真へとのめり込んでいきます。2度目の応募で再度佳作、3度目で遂に優秀賞を受賞。当時「写真新世紀」の公募は3ヶ月に一度行われており、カメラを始めてから受賞までわずか1年足らずでした。これが、大橋さんの人生を決定付けるターニングポイントに。 「最初の佳作受賞の時、荒木さんがコメントで『こいつは写真の才能があるかも』って書いてくれたんです。19歳のガキだったし、『才能』って言葉で完全に調子に乗っちゃったんですよ。これで仕事もきっとたくさん来て、写真でウハウハだなって思ってました(笑)」

薄暗い光に調節された仕事場
感情の動く瞬間が面白い

しかし、実際には才能があると思い込み舞い上がった青年に、仕事はほとんど来ませんでした。出版社に営業をしても「君にあげられる仕事は何もないよ」と門前払いされたことも。カメラに触れる機会も徐々に減り、倉庫番などのアルバイトに明け暮れていました。
受賞から1年が経った頃、「荒木経惟が選ぶ若手写真家」という雑誌の企画で声がかかります。それをきっかけに、週刊誌で袋とじのヌード写真を定期的に撮るようになり、さらに多くの仕事へと繋がったのです。
「バイトだけしていた1年間は、写真は全然撮っていませんでした。受賞したことがどんどん過去のことになって、写真への想いもかなり薄らぎましたね。でも仕事を頂いてカメラに触れていると、不思議と仕事以外の写真もまた撮るようになってきたんです」
『目のまえのつづき』や10人の出産シーンを収録した『いま』など、大橋さんは常に人間にカメラを向け続けてきました。そのごまかしのないストレートな写真には、生死を前にした人間の強烈なパワーが宿り、溢れ出ています。
「生まれたり死んだりって、人の感情がいちばん激しく動く時ですよね。そういった、感情の動く瞬間に強い興味を感じます」と大橋さん。彼の写真の迫力は、尊敬する荒木さんとの共通点でもあります。ところで、幼い頃から荒木さんの作品に惹かれていた大橋さんは、どんな部分に魅力を感じていたのでしょう?
「振り返ってみると多分、頭で考えられる領域を超えているところに惹かれていたんだと思うんです。どう考えても、体が先に反応しちゃっている写真だった。構図とかピントとか、そういう理屈では価値がはかれなくて、生々しさや生命力の強さに圧倒され、よく分からないけど惹き込まれていた感じです。それがとても気持ちのいい感覚だったんですよね」
今では広告や雑誌のスチールをはじめ、数多くの仕事をこなしている大橋さん。しかしその技術は学校や師から教わったものではなく、全て独学。そのため昔は多くの苦労もあったそう。
「仕事を始めた頃、スタジオでの撮影をお願いされたことがあったんです。僕は経験がなかったんですが、スタジオマンが全部設定してくれると思っていたので『大丈夫です!』ってすぐ受けて。でも、ストロボを同調させるという技術を知らなかったので、全然いい写真が撮れないんです。『これはヤバい』と思って、自然光なら問題なく撮れる、といきなり外に出て撮影しました。そんな状況を経ながら、技術を学んでいったんですね」
写真は被写体を生で触っているような感覚
写真家でありながら、PVなどの映像を手がけているのも特徴です。きっかけはスチール写真を撮影したモデルの担当マネージャーが、大橋さんの作品を知っていたことでした。その後電話で「PVを撮ってくれ」と突然依頼が。全く経験のない分野だったが、「ラッキー! って(笑)。だっていつか絶対やると思っていたし、やりたかったんですよ」

瞬間を切り取る写真と、連続する時間を追い続ける映像。フレーミングに要素を収めるという点では似ていますが、抵抗はなかったのでしょうか?
「もちろん違いはあるし技術的な問題は今もあるけど、抵抗は全然なかったです。結局は撮りたいもののイメージを押さえるというだけで、それが動いているか止まっているかの違いだけ」
では写真と映像の違いとは?
「映像はある意味、瞬間を『束』で捉えることが出来ますが、写真は100分の1秒というような単位で瞬間を捉えていくんだと思います。ムービーであろうとスチールであろうと、カメラの捉えている内容に違いは無いと思うのですが、『捉えている瞬間』の長さが違うんですね。ある瞬間を止めることで画に定着させる写真の性質は、現実を非現実へ変えてしまうようなところがあります。人間は時間を止められないので、時間を止めることが出来る写真というものにロマンを感じているんじゃないでしょうか。写真を撮るときは、被写体を生で触っているような感覚が強いです」
現在新しい写真集を制作中。テーマはズバリ「性」です。人間・生命・感情を追い続けて来た大橋さんにとって、これもまた避けられない題材のよう。
「今までも偶然と思いつきで写真集を作っているんですよ。ただ僕にとって、人間という生き物に興味を持っていれば、写真集の内容が『性』を中心にしたものになるのはまったく自然なことなんです」
手の届かないもの、自分の理解や思考を超えた先にあるものを追い求める大橋さん。これからはどんな写真を撮り続けたいと思っているのでしょう?
「単純に、自分が気持ち良くなれるものが撮りたいです。仕事は別ですが、自分の作品は好き勝手にやるのが全て。そうじゃなければ、なぜやっているのか分からないですし。自分を気持ち良くしてくれるものが、今後も写真であり続けてほしいですね」

写真制作のために仕立てられたような部屋

日当りがよく、ベランダからの眺めや近所の学校から聞こえてくる賑やかな声が気に入っているという自宅兼事務所。仕事部屋にお邪魔すると、書類が山積みになった大きな作業机、カメラを保管する防湿庫、Macとモニター、プリンター、隅に置かれたたくさんの機材、……仕事に関係のないものはほとんどない、まさに制作のための場所といった印象です。写真やモニターの反射を防ぐため、普段は薄暗い状態のまま仕事をしているそう。今日は取材ということで、ブラインドを開けて明るくしてもらい、いよいよ大橋さんのヒミツ道具に迫ります!
ヒミツ道具1 ニコンD3X

長年キヤノンのフィルムカメラを使用していたものの、昨年夏にデジタルに移行。きっかけはデジタルを導入していないことで、広告の仕事が3つ連続で流れてしまったことでした。ニコンを選んだのは仕上がりがフィルムに近かったからだそう。
「これは好みの問題だと思うんですよ。例えばフィルムなら僕はフジの発色が好きだったけど、コダックの柔らかい色が好きな人もいたし。印画紙にプリントした際に出るフィルムならではの生々しさや強さも好きなんですが、デジタルの良さもたくさんあります。特に現場での便利さは圧倒的に違いますね。だから一概に比較することはできなくて、それぞれ別物という感覚なんです」
ヒミツ道具2 ドライキャビン

湿度を低く保ち、カメラやフィルムをカビから守る防湿庫。過去に撮ったフィルムや、今はあまり使用しなくなったカメラ・レンズなども保管されています。
「シンプルなのがいいかなと思って、このボックスを10年前にひとつ買ったんです。それから機材が増えると、同じものを年々買い足していきました。10年前と全然デザインが変わっていないのがいいところですね(笑)」
ヒミツ道具3 ペンタブレット

知人に勧められたことにより使い始めたペンタブレット。マスクの作成や顔のシワ取りなど、細かいレタッチはアシスタントさんにお願いすることが多いものの、色調整等に関しては必ず、自分で行っています。Macやモニターとセットで購入し、販売店で「今すぐ使いたいんです!」とお願いしたところ、エクスプレスパッドのカスタマイズまで店員さんが設定してくれたそう。
「細かい作業はマウスだと難しいし、カメラマンならペンタブレットを使うほうが便利でしょ! って言われて買ったんです。例えば、背景だけ色を変えたい時など、操作が本当にラクなんですね。昔は印刷所でしかできなかった技術が、今は自分でできるし、しかも修正したのかどうかも分からないくらいに仕上げられる。その技術って、これからは絶対に必要だと思うんです。マウスは使わず、普段からペンタブレットで全て処理したほうが上達するというアドバイスを受けたので、もっと使いこなせるように日々練習中です」
ヒミツ道具4 マミヤRZ67

通常はスタジオで三脚を立てて使用することが多い大判カメラ。大橋さんは屋外で手持ち撮影をすることもあるそうです。解像度が大きいため、通常のカメラよりも硬めな仕上がりになるそうで、重厚感が欲しい時などに使用します。カメラ自体はフィルム用ですが、フェーズを付けることによりデジタルデータとして取り込める仕様になっています。ちなみにフェーズだけでウン百万!
「フェーズ、値段もかなり高いんですよ。いつになったら元が取れるんでしょう」
ヒミツ道具5 500mmの望遠レンズ(PENTAX)

無意識の人間の表情が撮りたい」と思い立ち2年前に購入。かなり望遠のため、人に気付かれることなく撮影出来るのがお気に入り。路上で、少し離れたところにいる被写体を撮影しているそう。
「望遠ならカメラマンを意識させないで撮影が出来るんです、無意識になっている人の表情はとても美しいんですね。そういう瞬間を捉えられると嬉しいですね」

作品の硬派なイメージとは裏腹に、常に笑顔で陽気にお話しして下さった大橋さん。「機材に凝るよりも、重要なのはどう撮るか」とその創作姿勢を説明して下さいましたが、ヒミツ道具は長年使い込まれたものが多く、大橋さんが愛情を注いでいることが感じられました。ぜひ、大橋さんの撮影機材を参考にしてみて下さい!